スマイルPJ通信・・・フリーペーパーに
今日の種差・・・日の出時刻が
 1月のブログを見ると、1か月前の日の出が6:56、日の入りが16:30でした。
1月のブログを見ると、1か月前の日の出が6:56、日の入りが16:30でした。今朝は、6:32日の出、日の入り時刻は17:05のようです。太陽のありがたさを実感します。
太陽の子、30名があいさつ運動やボランティア清掃を開始しています。放送委員の朝の練習の声が響いています。校内の太陽の子だけでなく、外遊びの好きな太陽の子にしていきたいと思います。
昨日、芝生地の雪の上に、そりの跡がついていました。子どもたちが遊んだのでしょうか。白浜漁港では、コクガンの群れを見つけました。ダイビングして何かを食べているようでした。30秒くらいは潜水している感じです。何もない遊歩道も良いものです。



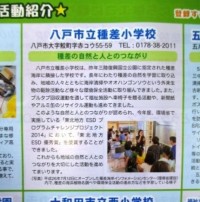 青森県は「もったいない・あおもり県民運動」を実施しており、その取組をフリーペーパーとして発行しています。№5には、本校の環境教育の取り組みも紹介されています。
青森県は「もったいない・あおもり県民運動」を実施しており、その取組をフリーペーパーとして発行しています。№5には、本校の環境教育の取り組みも紹介されています。 授業のおしまいは、紙コップギター演奏会でした。ドレミの音階もしっかりとることができるんですよ。もっと大きな紙コップで、大きなギターを作れば、来年の学習発表会で披露できるかな?ラッスンゴレライ?とか、あったかいんだから~などど歌っていました。このフレーズ、流行っているらしいです。
授業のおしまいは、紙コップギター演奏会でした。ドレミの音階もしっかりとることができるんですよ。もっと大きな紙コップで、大きなギターを作れば、来年の学習発表会で披露できるかな?ラッスンゴレライ?とか、あったかいんだから~などど歌っていました。このフレーズ、流行っているらしいです。
 紙コップの展開図を調べたり、上の部分を開いたり、底を切り落としたり・・・。分解したり、上を切ったものと比べたり、水を入れたり・・・。
紙コップの展開図を調べたり、上の部分を開いたり、底を切り落としたり・・・。分解したり、上を切ったものと比べたり、水を入れたり・・・。 おそるおそるでしたが、のってみました。すごいすごい!と言いながら。
おそるおそるでしたが、のってみました。すごいすごい!と言いながら。 理科クラブの実験でしょうか、紙コップ1個の上に板をのせ、上にのっていました。すぐつぶれてしました。
理科クラブの実験でしょうか、紙コップ1個の上に板をのせ、上にのっていました。すぐつぶれてしました。 天気がよく、芝生地に雪もたっぷり残っているので、竹スキーをのりました。そこへ中1が6名がそり持参で来たので、一緒に雪遊びをしました。どちらが一番長い距離をすべるか競争しました。
天気がよく、芝生地に雪もたっぷり残っているので、竹スキーをのりました。そこへ中1が6名がそり持参で来たので、一緒に雪遊びをしました。どちらが一番長い距離をすべるか競争しました。
