JS壮行会・部活動見学会・・・6年児童小中野中へ
1年生学校探検・・・7名来室
1年生が7名、校長室探検にやってきました。「校長先生の希望は何ですか?」と1つ目の質問、1年生に学校経営方針を述べよ!と言われた感じがしてびっくりしました。
「334人、全校児童が安全・安心で、勉強や運動ができる学校にしていくことです。」と答えました。
写真は誰か、何のトロフイーか、小中野小はいつできたか、珍しいものお宝は何か等の質問攻めでした。聞きたいことがいっぱいあることは良いですね。好奇心や意欲の表れだと思い、うれしくなりました。1年生は、4月より確実に成長しています。毎日、朝、挨拶しながら子どもたちの顔を見ていますが、日に日にしっかりした受け答えになってきています。笑顔も良いですね。
時々、校長室経由で教室に登校する子もいます。どうぞ、子どもたちの居場所の一つにして活用ください。たまに、児童学習室にもなります。

「334人、全校児童が安全・安心で、勉強や運動ができる学校にしていくことです。」と答えました。
写真は誰か、何のトロフイーか、小中野小はいつできたか、珍しいものお宝は何か等の質問攻めでした。聞きたいことがいっぱいあることは良いですね。好奇心や意欲の表れだと思い、うれしくなりました。1年生は、4月より確実に成長しています。毎日、朝、挨拶しながら子どもたちの顔を見ていますが、日に日にしっかりした受け答えになってきています。笑顔も良いですね。
時々、校長室経由で教室に登校する子もいます。どうぞ、子どもたちの居場所の一つにして活用ください。たまに、児童学習室にもなります。

プール管理人さん・・・全校児童に紹介
引き渡し訓練・・・公民館側
引き渡し訓練・・・校庭側
書写指導・・・外部講師を招いて
スポーツテスト・・・1年ソフトボール投げ
命の教育・・・自分の目や耳で判断して
プール清掃
今日の5校時に6年生がプール清掃を行いました。
デッキブラシやたわしを使ってプールの底や壁面、プールサイドをきれいにしました。
汚れが取れるたびに、6年生は喜んでいました。
6年生のみなさん、ありがとうございました。

デッキブラシやたわしを使ってプールの底や壁面、プールサイドをきれいにしました。
汚れが取れるたびに、6年生は喜んでいました。
6年生のみなさん、ありがとうございました。

2017/06/07 14:30 |
この記事のURL |
ボランティア教育活動




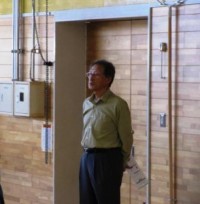 29年度もプール管理のお仕事を、堀内さんにお願いをしました。今朝、児童に紹介し、約束を守って、楽しい水泳、プール利用を進めていくことを確認し合いました。
29年度もプール管理のお仕事を、堀内さんにお願いをしました。今朝、児童に紹介し、約束を守って、楽しい水泳、プール利用を進めていくことを確認し合いました。




