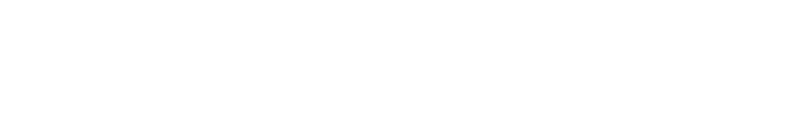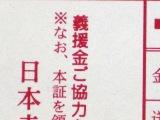動き出す子供たち
入学式準備・・・新5・6年頑張る!
じっくり時を待つ・・・自分たちで何ができるか!
各校でも大震災の義援金への協力をし始めたようです。本校では4年生が作文に、自分たちで何かできないか、電気の節電、灯油の節約(1階が使えず現在我慢しています。)・・・。
募金の話も出ていました。集めるのは簡単ですが、何のためにお願いするのか、範囲は、送り先は、何にどう使ってほしいのか等、子どもたちに十分話し合わせたいと思います。送って終わりでなく、最後までそのお金がどう使われ、どう役だったのかを見届けることが募金した人のつとめではないでしょうか。
4年生が、5年生に進級した4月にアクションを起こしてほしいですね。そして、全校での取り組みにしていきましょう。Love In Action!
募金の話も出ていました。集めるのは簡単ですが、何のためにお願いするのか、範囲は、送り先は、何にどう使ってほしいのか等、子どもたちに十分話し合わせたいと思います。送って終わりでなく、最後までそのお金がどう使われ、どう役だったのかを見届けることが募金した人のつとめではないでしょうか。
4年生が、5年生に進級した4月にアクションを起こしてほしいですね。そして、全校での取り組みにしていきましょう。Love In Action!
学校再開・・・子どもあっての学校です!
子どもの力を引き出す・・・意欲、向上心、継続
国語の発展・・・金子みすゞの絵本の読み聞かせを
3年生の国語の教科書に金子みすゞさんの詩が何編か出てきます。「ほしとたんぽぽ」は暗唱するぐらい勉強しました。
学年末ですので、下の学年に対して何かできなかと考えさせたところ、読み聞かせをしたい、ということになりました。3年生が、1・2年の教室へ出向き、絵本を持って読み聞かせを行います。
早速、誰がどの作品を担当するかを決めました。「ほしとたんぽぽ」という絵本には15編の詩がありました。19名ですので、4人が誰かと同じ作品になります。暗記したり、音読練習をしたりする前に、金子みすゞ生誕100周年記念のCDを聴くことになりました。皆、真剣です。
間の取り方やアクセントをまねしようと頑張っています。普段は、読み聞かせボランティアの方々のお話を聴いているので、やりたいと思ったのでしょうね。

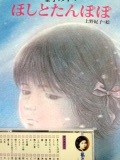
このような子どもによる文化的活動もできるように支援してききます。表現力の向上につながりますので。
学年末ですので、下の学年に対して何かできなかと考えさせたところ、読み聞かせをしたい、ということになりました。3年生が、1・2年の教室へ出向き、絵本を持って読み聞かせを行います。
早速、誰がどの作品を担当するかを決めました。「ほしとたんぽぽ」という絵本には15編の詩がありました。19名ですので、4人が誰かと同じ作品になります。暗記したり、音読練習をしたりする前に、金子みすゞ生誕100周年記念のCDを聴くことになりました。皆、真剣です。
間の取り方やアクセントをまねしようと頑張っています。普段は、読み聞かせボランティアの方々のお話を聴いているので、やりたいと思ったのでしょうね。

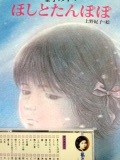
このような子どもによる文化的活動もできるように支援してききます。表現力の向上につながりますので。
引き継いでいく・・・4年5年が会場準備を!
いつもは6年生が様々な行事の準備をしてくれましたが、3月からは在校生が引き継ぎます。今朝、早速4年と5年が参観日全体会用にパイプ椅子並べをしてくれました。このように徐々にバトンタッチしていくのですね。その時、6年生は朝のボランティア清掃(6年間使った校舎に感謝の意味を込め、各自思い思いの場所の掃除をしている。)を黙々とこなしていました。なんだか6年生の目が寂しいような嬉しいような複雑な目をしていたように感じました。
いいんです。これが卒業式の呼びかけにある、「バトンタッチ」「後を引き継いで~」という言葉につながるのです。4年、5年もこのような仕事や動きを通して自覚していくのですね。とてもよい場面でした。

いいんです。これが卒業式の呼びかけにある、「バトンタッチ」「後を引き継いで~」という言葉につながるのです。4年、5年もこのような仕事や動きを通して自覚していくのですね。とてもよい場面でした。


新1年生が一番興味を示した物・・・恐竜!
五人囃子の並び・・・調べてきた子がいました!
新1年生が来ると・・・頑張っている姿見せたい!
和が7になっていないサイコロ
サイコロの目のきまりとして、「向かい合う2面の和が7」。学校のサイコロの中には、適当に作ったものもあり、子供たちはめざとく見つけます。(青がへん)
「どうして7なのかな?」・・・これが子どもたちの立体以外の追究です。平均を学習した5年なら分かるでしょう。4年生なら「1+2+3+4+5+6=21」「21÷3(ペア)=7」「1+2+・・・の並びをみて、1と6、3と4、2と5のペアを見つけて、7」ぐらいは気付くかな。
6年生になら、「1~6の目のでる確率は皆同じ?」と聞いてみましょう。これを証明するのは難しいですが、1の目の赤と2の目の黒ぽつ2個をよく見ると、1の目のほうのくぼみが大きです。ということは、サイコロの重心は中央でなくずれているのです。ふって確かめてみれば分かりますが、2と5に重心が偏っている感じがします。ですから、○の目が多少出やすい?と言えるのかもしれません。こんなことも追究できる子に育てたいものです。
この子たちは、教室内の算数でなく、教室以外での算数です。教室以外はどんどん子どもの任せたいものです。授業で使える内容があれば、使えばよいのす。
各校CRTの結果が届いて、落ちてる箇所を分析し、対策を講じてる段階fでは、このような追究活動は無理なのかもしれませんね。
「どうして7なのかな?」・・・これが子どもたちの立体以外の追究です。平均を学習した5年なら分かるでしょう。4年生なら「1+2+3+4+5+6=21」「21÷3(ペア)=7」「1+2+・・・の並びをみて、1と6、3と4、2と5のペアを見つけて、7」ぐらいは気付くかな。
6年生になら、「1~6の目のでる確率は皆同じ?」と聞いてみましょう。これを証明するのは難しいですが、1の目の赤と2の目の黒ぽつ2個をよく見ると、1の目のほうのくぼみが大きです。ということは、サイコロの重心は中央でなくずれているのです。ふって確かめてみれば分かりますが、2と5に重心が偏っている感じがします。ですから、○の目が多少出やすい?と言えるのかもしれません。こんなことも追究できる子に育てたいものです。
この子たちは、教室内の算数でなく、教室以外での算数です。教室以外はどんどん子どもの任せたいものです。授業で使える内容があれば、使えばよいのす。
各校CRTの結果が届いて、落ちてる箇所を分析し、対策を講じてる段階fでは、このような追究活動は無理なのかもしれませんね。