今年度最後の計算テスト
つよい子6 NO.108 1・2年体育
つよい子6 NO.107 透明な箱
算数で、「はこの形」について学習しています。
今日はストローと粘土で透明な箱(?)作りに挑戦しました。
ただし,ストローや粘土は何個必要か申し込んで借りる約束です。
作っていると,
「あ~,粘土が足りない!」
「あれ,ストローが多い・・・。」
「先生,赤のストローをあと2本ください。」
多かったり少なかったり・・・・。

何度かストローの本数を訂正しながらも,完成していきました。

みんなが使った粘土やストローの数を確認してみると,
「粘土は全部8個だ!」
「ストローは,どの箱もあわせると12本だね。」
「スローは0本か4本か8本か12本になってる!」
すごい法則を発見です!
でも,この法則にぴったりの数の粘土とストローを借りたはずなのに,
なぜかきちんとした箱にならずに悩んでいます。
.JPG)
「ストローの組み合わせが悪いんじゃない?」
みんなで一緒に考えて,無事完成しました。
やっぱりみんなで見つけた法則は,まちがっていなかった!

今日はストローと粘土で透明な箱(?)作りに挑戦しました。
ただし,ストローや粘土は何個必要か申し込んで借りる約束です。
作っていると,
「あ~,粘土が足りない!」
「あれ,ストローが多い・・・。」
「先生,赤のストローをあと2本ください。」
多かったり少なかったり・・・・。

何度かストローの本数を訂正しながらも,完成していきました。

みんなが使った粘土やストローの数を確認してみると,
「粘土は全部8個だ!」
「ストローは,どの箱もあわせると12本だね。」
「スローは0本か4本か8本か12本になってる!」
すごい法則を発見です!
でも,この法則にぴったりの数の粘土とストローを借りたはずなのに,
なぜかきちんとした箱にならずに悩んでいます。
.JPG)
「ストローの組み合わせが悪いんじゃない?」
みんなで一緒に考えて,無事完成しました。
やっぱりみんなで見つけた法則は,まちがっていなかった!




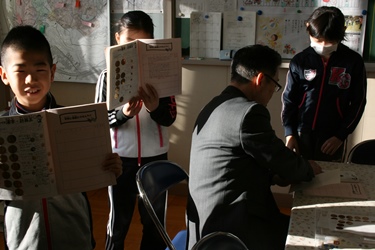




.JPG)
.JPG)
.JPG)

.JPG)












