学習発表会
今日は、気温が上がらず、時より雨が降ってくる中でしたが、無事に学習発表会を実施することができました。久しぶりに地域の来賓の方々を招待できました。子どもたちは、自分の力を100%出し切り、お客様に元気と感動を与えることができました。


















2023/10/21 14:20 |
この記事のURL |
学習発表会予行
10月18日、学習発表会の予行を行いました。各学年とも工夫された内容で、本番までには、さらに完成度をあげると思います。今日は、よくがんばりました。




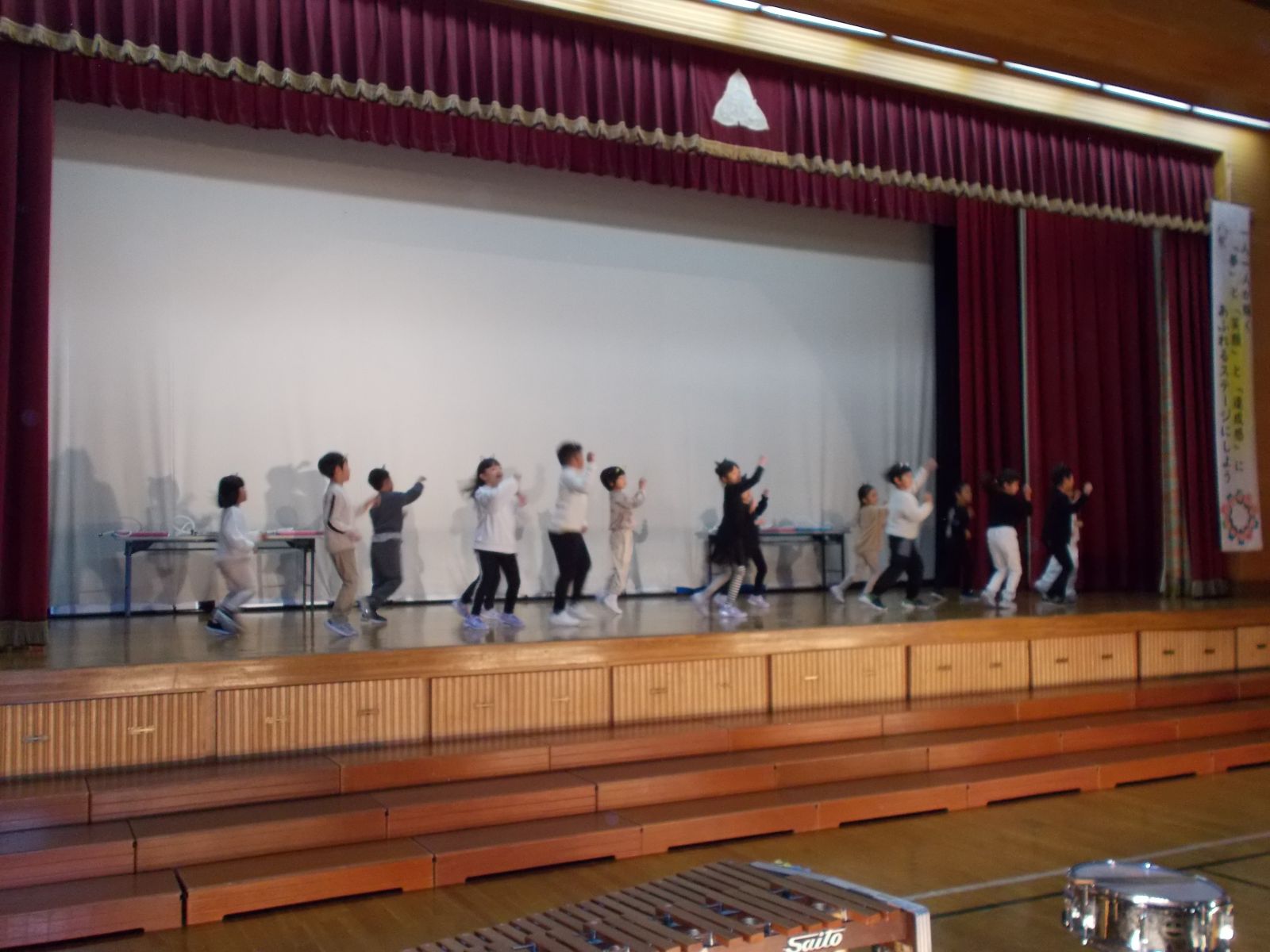









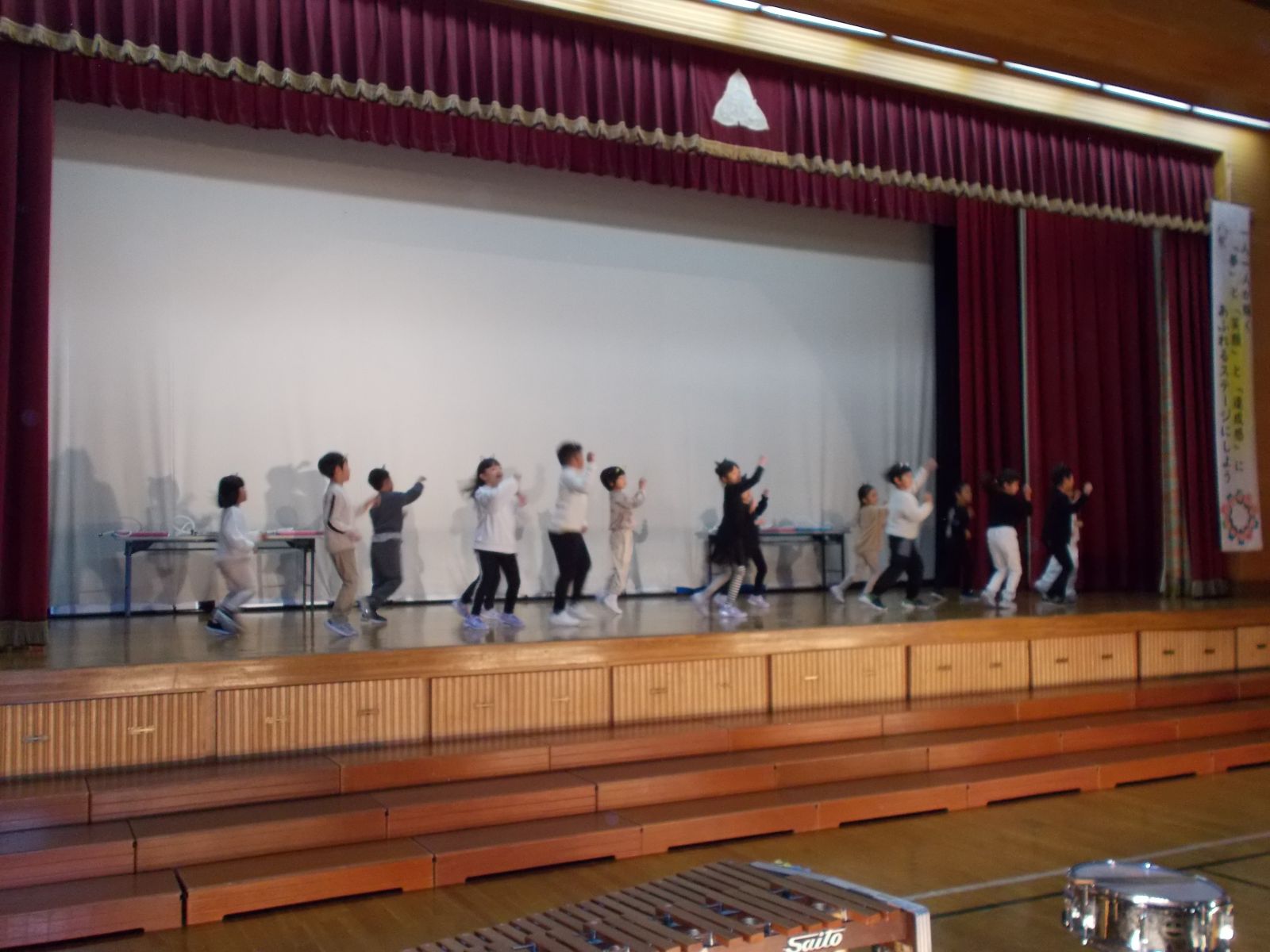





2023/10/18 17:20 |
この記事のURL |
校内マラソン大会
10月5日、校内マラソン大会を実施しました。午前中に雨が降る天気予報のため、移動時間等を考慮して、場所を校庭に変更して行いました。参加した子どもたち全員が最後まであきらめずに走りきることができました。大きな拍手を送りたいと思います。また、場所の変更等にも関わらず応援に駆けつけてくださった保護者の皆様、ありがとうございました。
























2023/10/05 13:20 |
この記事のURL |
学校教育課訪問
10月3日の午前中、学校教育課訪問がありました。5名の方々来校され、授業の様子を参観されました。
















2023/10/04 10:50 |
この記事のURL |


