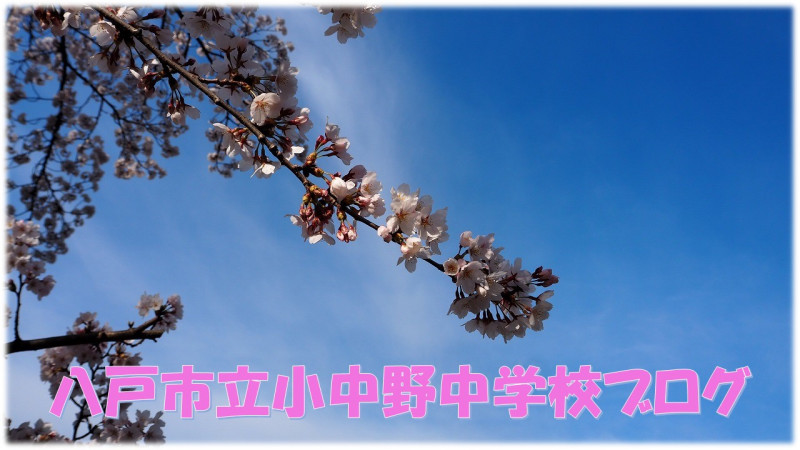夏季大会に向けて Part7
「夏季大会に向けて」と題してお送りしてきたこのブログ企画も、
今回が最終回となりました。
トリを務めるのは吹奏楽部です。

例年どおりの夏季大会であれば野球の応援で高らかに音を出し、
全校の士気を高めてきた吹奏楽部。しかしここ1~2年は、音を
出すことができません。それでも部員たちは、自分たちができる
ことを探しながら練習に励んできました。
.JPG)
明日の壮行会に向けて入場曲の練習に余念がありません。一人
1パートなので、責任重大ですが楽しんで演奏しています。
.JPG)
見えずらいのですが、フェイスガードを付けながら練習しています。
明日の壮行会では、きっと運動部に負けない気迫で演奏してくれる
ことでしょう。楽しみです。
さあ、明日は壮行会。”Team KONAKANO"として、一丸となって
臨みます。乞うご期待!
今回が最終回となりました。
トリを務めるのは吹奏楽部です。

例年どおりの夏季大会であれば野球の応援で高らかに音を出し、
全校の士気を高めてきた吹奏楽部。しかしここ1~2年は、音を
出すことができません。それでも部員たちは、自分たちができる
ことを探しながら練習に励んできました。
.JPG)
明日の壮行会に向けて入場曲の練習に余念がありません。一人
1パートなので、責任重大ですが楽しんで演奏しています。
.JPG)
見えずらいのですが、フェイスガードを付けながら練習しています。
明日の壮行会では、きっと運動部に負けない気迫で演奏してくれる
ことでしょう。楽しみです。
さあ、明日は壮行会。”Team KONAKANO"として、一丸となって
臨みます。乞うご期待!
2022/06/15 16:40 |
この記事のURL |
夏季大会に向けて Part6
夏季大会まであと4日。そして、壮行会まであと2日のきょうは
卓球部の活動の様子を紹介します。

体育館半面に並べられた9台の卓球台に向かう部員の姿は真剣
そのもの。このときは、声をかけあいながら「ドライブブロック」
という練習に取り組んでいました。
.JPG)
卓球はわずかな回転のかけ方で勝負が決まることがあるので
ドライブの練習はとても重要です。顧問の市川先生から
「打点に気を付けて。」と声が飛んでいました。
.JPG)

休憩の声がかかると、学年問わずボール拾いに走ります。
チームワークの良さが、そんなところにも表れる卓球部も
要チェックですね。
卓球部の活動の様子を紹介します。

体育館半面に並べられた9台の卓球台に向かう部員の姿は真剣
そのもの。このときは、声をかけあいながら「ドライブブロック」
という練習に取り組んでいました。
.JPG)
卓球はわずかな回転のかけ方で勝負が決まることがあるので
ドライブの練習はとても重要です。顧問の市川先生から
「打点に気を付けて。」と声が飛んでいました。
.JPG)

休憩の声がかかると、学年問わずボール拾いに走ります。
チームワークの良さが、そんなところにも表れる卓球部も
要チェックですね。
2022/06/14 17:50 |
この記事のURL |
花壇整備(PTA環境委員の皆様)
令和3年6月14日(火)8:30~
今年度1回目のPTA環境委委員の皆様による
花壇整備が行われました。
20名ほどの方々が集まってくださいました。
感謝感謝です。
.JPG)
早速、作業に取り掛かってくださいました。
駐車場側の東校舎前の花壇と、玄関前のフラワーポットへの
花の植え込み作業が、手際よく進みます進みます。
初めは土おこしをして、肥料撒き、雑草取りです。
チームワークも抜群です。
.JPG)
10日間以上、肌寒い曇天の日が続いていたため、
天候が心配されましたが。青空が広がっています。
.JPG)
苗をレイアウトして置いていきます。その後、
丁寧に植え込み、水をたっぷり撒いてあげます。
乾いた白い土が水を含んで黒く湿っていきます。
.JPG)
水を含んだ土で生き生きと咲き始めたオレンジ色と
黄色のマリーゴールドが鮮やかです。
隣の「哲学の森」では、技能主事のGさんが、
草刈りをしてくださっています。
.JPG)
中天から低空にかけて少しずつ変わる空の青の
コントラストの美しさに、心惹かれます。
吸い込まれそうな空です。
.JPG)
無事に植え付けを終えた花壇がとてもきれいです。
これから、葉を伸ばし花を増やして、にぎやかに
玄関前の景色を彩ってくれることでしょう。
環境委員の保護者の皆様、お手伝いの方もいたと思います。
本当にありがとうございました。
ちなみに…、
校長先生も一緒に花植えを頑張ってました…。
今年度1回目のPTA環境委委員の皆様による
花壇整備が行われました。
20名ほどの方々が集まってくださいました。
感謝感謝です。
.JPG)
早速、作業に取り掛かってくださいました。
駐車場側の東校舎前の花壇と、玄関前のフラワーポットへの
花の植え込み作業が、手際よく進みます進みます。
初めは土おこしをして、肥料撒き、雑草取りです。
チームワークも抜群です。
.JPG)
10日間以上、肌寒い曇天の日が続いていたため、
天候が心配されましたが。青空が広がっています。
.JPG)
苗をレイアウトして置いていきます。その後、
丁寧に植え込み、水をたっぷり撒いてあげます。
乾いた白い土が水を含んで黒く湿っていきます。
.JPG)
水を含んだ土で生き生きと咲き始めたオレンジ色と
黄色のマリーゴールドが鮮やかです。
隣の「哲学の森」では、技能主事のGさんが、
草刈りをしてくださっています。
.JPG)
中天から低空にかけて少しずつ変わる空の青の
コントラストの美しさに、心惹かれます。
吸い込まれそうな空です。
.JPG)
無事に植え付けを終えた花壇がとてもきれいです。
これから、葉を伸ばし花を増やして、にぎやかに
玄関前の景色を彩ってくれることでしょう。
環境委員の保護者の皆様、お手伝いの方もいたと思います。
本当にありがとうございました。
ちなみに…、
校長先生も一緒に花植えを頑張ってました…。
2022/06/14 12:40 |
この記事のURL |
夏季大会に向けて Part5
Part5となる今回は、男女バレーボール部の活動をお知らせします。
.JPG)
この日は、高校生の先輩方が夏季大会前の後輩のためにわざわざ
駆けつけ、練習相手を買って出てくれていました。
試合形式の練習ができるのは、この時期とてもありがたいものです。
.JPG)
男子も女子も、「ナイスカバー!」「ライト!「レフト!」と
声を掛け合いながら、モチベーションを上げています。
.JPG)
外部コーチの下舘裕さんから飛ぶ指示にも勢いよく返事を返す、
元気なバレー部員。
様々な思いをボールに込めて、つないでくれることでしょう。
.JPG)
この日は、高校生の先輩方が夏季大会前の後輩のためにわざわざ
駆けつけ、練習相手を買って出てくれていました。
試合形式の練習ができるのは、この時期とてもありがたいものです。
.JPG)
男子も女子も、「ナイスカバー!」「ライト!「レフト!」と
声を掛け合いながら、モチベーションを上げています。
.JPG)
外部コーチの下舘裕さんから飛ぶ指示にも勢いよく返事を返す、
元気なバレー部員。
様々な思いをボールに込めて、つないでくれることでしょう。
2022/06/14 10:00 |
この記事のURL |
夏季大会に向けて Part4
ここまで3回運動部の様子を紹介してきましたが、今回は夏季大会を
支える、そして本校応援団の大黒柱ともいえる報道部の様子を紹介
します。

感染症対策のため、今回全校応援ができる競技は、本校の場合野球
のみ。しかも、吹奏楽を入れることができません。声を出すことも
できません。それでも報道部の皆さんは、ペットボトルを使って
選手を鼓舞する応援をしようと練習に励んでいます。
.JPG)
試合の流れに合わせて、タイミングよく、というのはなかなか難しい
ものです。しかも全校の応援をリードしなければなりません。

てのひらを真っ赤にしながら練習に励む報道部の活躍も乞うご期待!
支える、そして本校応援団の大黒柱ともいえる報道部の様子を紹介
します。

感染症対策のため、今回全校応援ができる競技は、本校の場合野球
のみ。しかも、吹奏楽を入れることができません。声を出すことも
できません。それでも報道部の皆さんは、ペットボトルを使って
選手を鼓舞する応援をしようと練習に励んでいます。
.JPG)
試合の流れに合わせて、タイミングよく、というのはなかなか難しい
ものです。しかも全校の応援をリードしなければなりません。

てのひらを真っ赤にしながら練習に励む報道部の活躍も乞うご期待!
2022/06/13 18:20 |
この記事のURL |
夏季大会に向けて Part3
「夏季大会に向けて」の第3弾、今回は剣道部の様子をお伝えします。

気迫のこもった声が、道場に響き渡っています。
面を付けているので表情はわかりませんが、背中から緊迫感が伝わります。
.JPG)
外部コーチの高橋直浩前校長先生と山村益弘さんの御指導の下、
淀みなき練習が続いています。
取材をしているこちらの背中もしゃんとする雰囲気です。

そんな先輩の姿に刺激され、黙々と素振りに励む1年生。
自分の思いを竹刀に込めて夏季大会で健闘してくれることを期待しています。

気迫のこもった声が、道場に響き渡っています。
面を付けているので表情はわかりませんが、背中から緊迫感が伝わります。
.JPG)
外部コーチの高橋直浩前校長先生と山村益弘さんの御指導の下、
淀みなき練習が続いています。
取材をしているこちらの背中もしゃんとする雰囲気です。

そんな先輩の姿に刺激され、黙々と素振りに励む1年生。
自分の思いを竹刀に込めて夏季大会で健闘してくれることを期待しています。
2022/06/13 09:20 |
この記事のURL |
市中体夏季大会に向けて Part2
今回はテニス部の練習風景を紹介します。
取材した時間帯が練習開始後まもなくだったこともあり、基礎練習に
励んでいました。
.JPG)
和やか、かつ真剣な表情でボールを追いかけるテニス部の皆さんです。
.JPG)
顧問の一ノ渡先生からの、「ミスを減らすように、そして集中して!」
というお話に、真摯な態度で耳を傾けています。
.JPG)
すべての競技において、基礎練習は試合の流れを左右するほど大切な
メニューです。
テニス部の皆さんの姿からそのことを思い出しました。
頑張れ!
取材した時間帯が練習開始後まもなくだったこともあり、基礎練習に
励んでいました。
.JPG)
和やか、かつ真剣な表情でボールを追いかけるテニス部の皆さんです。
.JPG)
顧問の一ノ渡先生からの、「ミスを減らすように、そして集中して!」
というお話に、真摯な態度で耳を傾けています。
.JPG)
すべての競技において、基礎練習は試合の流れを左右するほど大切な
メニューです。
テニス部の皆さんの姿からそのことを思い出しました。
頑張れ!
2022/06/10 14:50 |
この記事のURL |
市中体夏季大会に向けて Part1
6月18日から始まる夏季大会が8日後に迫ってきました。
そこで、各部の練習の様子をちょこっとずつレポートしていきます。
(ただし、練習の邪魔にならないよう、離れたところで取材して
おりますので、かなりざっくりです。御容赦ください。)
まずは、県春季大会の雪辱に燃える野球部から。
.JPG)
気持ちを高めながら、部活動指導員である種子浩好さんからの
指示に耳を傾けています。
.JPG)
声をかけながら軽快にボールをさばいていきます。
.JPG)

夕日の中、声も気持ちも高まってきた野球部の活躍が楽しみです。
感染対策を講じながらの夏季大会、本校で唯一全校応援の期待がかかる
野球部でした。
そこで、各部の練習の様子をちょこっとずつレポートしていきます。
(ただし、練習の邪魔にならないよう、離れたところで取材して
おりますので、かなりざっくりです。御容赦ください。)
まずは、県春季大会の雪辱に燃える野球部から。
.JPG)
気持ちを高めながら、部活動指導員である種子浩好さんからの
指示に耳を傾けています。
.JPG)
声をかけながら軽快にボールをさばいていきます。
.JPG)

夕日の中、声も気持ちも高まってきた野球部の活躍が楽しみです。
感染対策を講じながらの夏季大会、本校で唯一全校応援の期待がかかる
野球部でした。
2022/06/10 09:40 |
この記事のURL |
6月全校朝会&野球部県大会
6月6日(月) 曇り時々雨
まだ梅雨入り前なのですが、先週から梅雨空を思わせる
どんよりとした天候が続いています。先日、衣替えを、
済ませたばかりなのですが、肌寒さすら感じます。
本格的な夏は、まだまだ先のようです。
さて、本日は6月の全校朝会が行われました。
.JPG)
内容は春季大会の表彰と校長先生からのお話です。
表彰は、春の大会で準優勝を果たした野球部です。
.JPG)
そして、校長先生のお話です。
.JPG)
今月のお話は、大きく2点でした。
一つ目の内容は、18日から始まる市夏季大会について
です。コロナ禍で、2年間部活動の大会に関して苦しい
思いをしてきた、そして昨年・一昨年の先輩方の悔しさ
を知る3年生に向けて語り掛けるところから、お話が始
まりました。その上で運動部・文化部、3年生・1年生、
選手も応援も関係なく、誰にとっても大切な大会である
ということ、誰が欠けてもいけない大会であることなど、
夏季大会への思い、願いが伝えられました。
二つ目は、恒例の本の紹介です。 今月の本は…、
『弱いメンタルに劇的に効くアスリートの言葉』
という本です。図書室にある黄色い本のようです。
2人のアスリートの言葉も併せて紹介されました。
・「努力しても報われるわけじゃない。でも、努力しない
と報われない」(プロボクサー 村田諒太選手)
・「ジャンプ台にしても、私たち選手が朝、会場につく前
よりもっと早く、たくさんの人が来て作ってくれている
から飛べるんですね。それを考えると感謝せざるを得な
いというか、感謝せずにはいられないです。」
(スキージャンプ 高梨沙羅選手)
素敵な言葉ですね。素敵な思いです。
「心・技・体」が全て整わなければ、自分の納得できる
パフォーマンスは発揮できないのでしょう。ただし、
その中でも、最も大切なのは「心」なのだということを
一流のアスリートの方の言葉だからこそ、より重く、
より深く、胸に突き刺さります。
ところで、表彰された野球部が、この土・日、
津軽方面で行われた県大会を戦ってきました。
結果は、1回戦、弘前代表の津軽中と戦って、8-0の
スコアで残念ながら敗れてしまいましたが、次につなが
る内容だったようです。県大会の場を経験できたことが
かけがえのない財産です。
野球部の県大会の試合の様子です。
.JPG)
.JPG)
勝ち上がり、夏の県大会のステージで、
きっと、リベンジを果たしてくれるでしょう。
夏への期待が高まります。
どの部も頑張れ!
まだ梅雨入り前なのですが、先週から梅雨空を思わせる
どんよりとした天候が続いています。先日、衣替えを、
済ませたばかりなのですが、肌寒さすら感じます。
本格的な夏は、まだまだ先のようです。
さて、本日は6月の全校朝会が行われました。
.JPG)
内容は春季大会の表彰と校長先生からのお話です。
表彰は、春の大会で準優勝を果たした野球部です。
.JPG)
そして、校長先生のお話です。
.JPG)
今月のお話は、大きく2点でした。
一つ目の内容は、18日から始まる市夏季大会について
です。コロナ禍で、2年間部活動の大会に関して苦しい
思いをしてきた、そして昨年・一昨年の先輩方の悔しさ
を知る3年生に向けて語り掛けるところから、お話が始
まりました。その上で運動部・文化部、3年生・1年生、
選手も応援も関係なく、誰にとっても大切な大会である
ということ、誰が欠けてもいけない大会であることなど、
夏季大会への思い、願いが伝えられました。
二つ目は、恒例の本の紹介です。 今月の本は…、
『弱いメンタルに劇的に効くアスリートの言葉』
という本です。図書室にある黄色い本のようです。
2人のアスリートの言葉も併せて紹介されました。
・「努力しても報われるわけじゃない。でも、努力しない
と報われない」(プロボクサー 村田諒太選手)
・「ジャンプ台にしても、私たち選手が朝、会場につく前
よりもっと早く、たくさんの人が来て作ってくれている
から飛べるんですね。それを考えると感謝せざるを得な
いというか、感謝せずにはいられないです。」
(スキージャンプ 高梨沙羅選手)
素敵な言葉ですね。素敵な思いです。
「心・技・体」が全て整わなければ、自分の納得できる
パフォーマンスは発揮できないのでしょう。ただし、
その中でも、最も大切なのは「心」なのだということを
一流のアスリートの方の言葉だからこそ、より重く、
より深く、胸に突き刺さります。
ところで、表彰された野球部が、この土・日、
津軽方面で行われた県大会を戦ってきました。
結果は、1回戦、弘前代表の津軽中と戦って、8-0の
スコアで残念ながら敗れてしまいましたが、次につなが
る内容だったようです。県大会の場を経験できたことが
かけがえのない財産です。
野球部の県大会の試合の様子です。
.JPG)
.JPG)
勝ち上がり、夏の県大会のステージで、
きっと、リベンジを果たしてくれるでしょう。
夏への期待が高まります。
どの部も頑張れ!
2022/06/06 11:20 |
この記事のURL |
5月の生徒朝会
令和4年5月30日(月) 晴れ ※強が強い…
空は晴れ渡っていますが、風の強い一日です。
夏を目の前に気圧の谷間がやってきているようです。
天気予報にも今週は雲と傘のマークが並んでいます。
5月の生徒朝会が行われました。
生徒総会を終え生徒会活動が軌道に乗り始めました。
まずは、計画されていた挨拶運動が始まっています。
野球部が先陣を切って行っています。
そして、今回から生徒朝会は各委員会の発表です。
こちらは、生活向上委員会と保健委員会が先陣を
きって発表しました。まずは生活向上委員会です。
生活向上委員会
.JPG)
.JPG)
生活向上委員会の発表は、学校生活の基本的な
ルールやマナーについてモデルや実演を交えて
の説明でした。さらに今年は、パワーポイント
を使うなどのバージョンアップのみならず、
なんと、動画を入れての発表でした。
保健委員会
.JPG)
.JPG)
保健委員会の発表は、これから迎える熱い夏を
前に、熱中症対策についての諸注意でした。
アドバイスというべきでしょうか。
こちらも、パワーポイントを使っていますが、
アニメーションを施すなど、ところどころに、
惹きつけるための工夫が施されています、
さらには健康クイズが数問出題され、自然な、
さりげない盛り上がりが朝から見られました。
ちなみに、出題された問題は…、
①朝ご飯と学習・体力との因果関係
②中学生の望ましい睡眠時間
③熱中症対策の正しい衣服調節
④飛沫とは何を指すのか
⑤正しい咳エチケットの在り方
だったと記憶しています。
それぞれ、三択問題で挙手制で行われました。
どの問題も正解者多数でしたね。
手のあげ方が、みんな自信に満ちていました。
発表する側、伝える側の創意工夫に拍手です。
いや、
「いいね!」をいっぱいあげたいですね。
空は晴れ渡っていますが、風の強い一日です。
夏を目の前に気圧の谷間がやってきているようです。
天気予報にも今週は雲と傘のマークが並んでいます。
5月の生徒朝会が行われました。
生徒総会を終え生徒会活動が軌道に乗り始めました。
まずは、計画されていた挨拶運動が始まっています。
野球部が先陣を切って行っています。
そして、今回から生徒朝会は各委員会の発表です。
こちらは、生活向上委員会と保健委員会が先陣を
きって発表しました。まずは生活向上委員会です。
生活向上委員会
.JPG)
.JPG)
生活向上委員会の発表は、学校生活の基本的な
ルールやマナーについてモデルや実演を交えて
の説明でした。さらに今年は、パワーポイント
を使うなどのバージョンアップのみならず、
なんと、動画を入れての発表でした。
保健委員会
.JPG)
.JPG)
保健委員会の発表は、これから迎える熱い夏を
前に、熱中症対策についての諸注意でした。
アドバイスというべきでしょうか。
こちらも、パワーポイントを使っていますが、
アニメーションを施すなど、ところどころに、
惹きつけるための工夫が施されています、
さらには健康クイズが数問出題され、自然な、
さりげない盛り上がりが朝から見られました。
ちなみに、出題された問題は…、
①朝ご飯と学習・体力との因果関係
②中学生の望ましい睡眠時間
③熱中症対策の正しい衣服調節
④飛沫とは何を指すのか
⑤正しい咳エチケットの在り方
だったと記憶しています。
それぞれ、三択問題で挙手制で行われました。
どの問題も正解者多数でしたね。
手のあげ方が、みんな自信に満ちていました。
発表する側、伝える側の創意工夫に拍手です。
いや、
「いいね!」をいっぱいあげたいですね。
2022/05/30 13:30 |
この記事のURL |