ボランティア・福祉
5年生のボランティア
5年1組福寿荘訪問
福寿草訪問・・・2回目
福寿草訪問・・・5年生
養命会との交流
高齢者疑似体験&車椅子体験・・・5年生
認知症サポーター養成講座・・・5年生が福祉教育の一環に!
本校5年生は,特別老人ホーム「福寿草」に出かけ,お年寄りとの交流や車椅子の寄贈等を行ってきました。
今回は,施設の職員の方々をお招きして,認知症とは何か,どう接することが大事なのかについて勉強しました。はじめに,紙芝居による認知症の説明があり,後半は寸劇を見ながら認知症の行動や特性について勉強しました。
子どもたちはこの養成講座を通して,「病気の勉強が大切なこと」「不安な気持ちを分かること」「きずつけないこと」「近所で見守ること」を知りました。
「病気になっても,いつだって心は生きているんだ!」という職員の方々のお話が一番心に残りました。
今回は,施設の職員の方々をお招きして,認知症とは何か,どう接することが大事なのかについて勉強しました。はじめに,紙芝居による認知症の説明があり,後半は寸劇を見ながら認知症の行動や特性について勉強しました。
子どもたちはこの養成講座を通して,「病気の勉強が大切なこと」「不安な気持ちを分かること」「きずつけないこと」「近所で見守ること」を知りました。
「病気になっても,いつだって心は生きているんだ!」という職員の方々のお話が一番心に残りました。



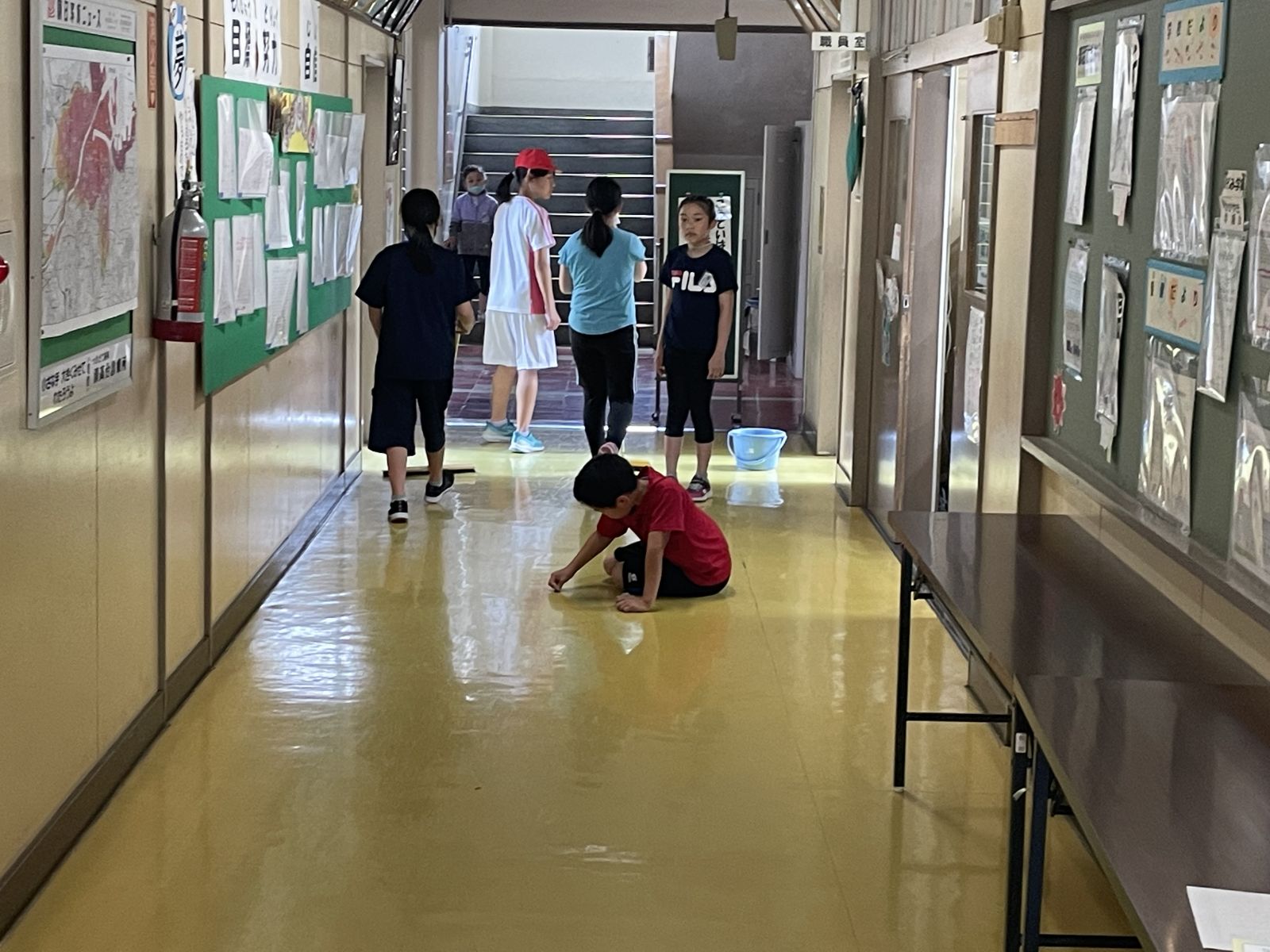

 5年1組が総合的な学習で学区にある老人福祉施設福寿荘を訪問しました。合唱やリコーダーを聞いていただいた後、班ごとに触れ合いを行いました。プレゼントを渡したり、昔の話を聞いたりして過ごしました。来週には5年2組が訪問します。
5年1組が総合的な学習で学区にある老人福祉施設福寿荘を訪問しました。合唱やリコーダーを聞いていただいた後、班ごとに触れ合いを行いました。プレゼントを渡したり、昔の話を聞いたりして過ごしました。来週には5年2組が訪問します。
























